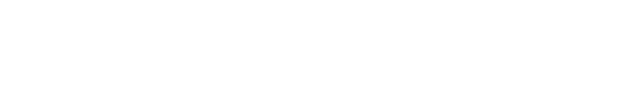当院の特徴
よりクリニックの特徴について
お子様からご高齢の方まで、皆様のより所となれるよう、心により添い、より良い医療を提供いたします
- 対話を大切にお子様からご高齢の方まで幅広く対応いたします
- CTなどの医療機器を導入することで診断精度を高めます
- IT機器を導入することで患者様の利便性を高めます
- 起立性調節障害、睡眠時無呼吸症候群、心理療法を要する不安障害など治療ニーズが高い疾患に幅広く対応いたします
- 病気や障害のみに主軸を置かず、生活を診ることをモットーに訪問診療もいたします
- 生活の場で診療を行うことで、通院への抵抗感や困難を減らし、患者様やご家族に安心していただいた状態で医療を提供いたします
当院で行っている治療
下記の症状や疾患に対応致します。子どもからご高齢の方まで幅
主な症状
- 気分が落ち込む
- 物事を楽しめなくなった
- 意欲が湧かない
- イライラしたりカッとしやすい
- 強迫症状がある(例:手洗いや入浴、確認行為を過剰にしてしまう)
- 人に注目される事を心配しすぎたり、注目されることを避けようとする
- 発作的に動悸や息苦しさ、過呼吸、めまいなどが現れる
- 年齢を重ねて物忘れが増えた
- 物忘れに伴う行動に困っている
- 夜眠れない
- 朝の寝起きが悪い
- 日中の眠気が強い
- 人とコミュニケーションを上手く取れない。
- 場の空気を読んだり人の気持ちを理解することが苦手
- 整理整頓が苦手
- お金や時間の管理が苦手
- 忘れ物や失くし物が多い
- 集中力が長続きせず気がそれやすい
- 「問題行動」を起こしてしまう
- 発達障害について相談したい
- 人がいないのに人の声が聞こえる
- 人に悪さをされている、悪口を言われている、見張られていると感じる
- 過去の傷つき体験について相談したい
- お酒が止められずアルコールの摂取量が増えている落ち着きがなくじっとしている事が苦手
- ゲームが止められない
- 学校にいけない・不登校
- ひきこもりの状態が続いている。
疾患など
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、不安障害、パニック障害、社交不安障害、強迫性障害、全般性不安障害、認知症・物忘れ、適応障害、神経症、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症、知的障害、摂食障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、アルコール依存症、ひきこもり、不登校、起立性調節障害、睡眠時無呼吸症候群、その他
自立支援医療制度(精神通院医療)がご利用できます。
●自立支援医療制度(精神通院医療)とは?
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
この制度を利用することで、原則として医療費の自己負担が1割になります。さらに、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されるため、「医療費が高額になって生活が苦しい…」といった心配を軽減することができます。申請は、区役所福祉課、総合出張所です。医師の自立支援診断書が必要となるため、ご利用を検討される際は、受付にてお声掛けください。
●どんな人が対象になるの?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める精神疾患を有する方で、継続的な通院による治療が必要な方。
具体的には、以下のような病気で治療を受けている方が対象となることが多いです。
統合失調症
うつ病、双極性障害などの気分障害
不安障害(パニック障害、社交不安障害など)
適応障害
その他、精神科医が継続的な治療が必要と認めた精神疾患
年齢制限はなく、所得制限はありますが、多くの方が利用できる制度となっています。
●医療費はどうなるの?
通常、病院やクリニックを受診した際の医療費は、健康保険の種類に応じて1~3割が自己負担となります。しかし、自立支援医療制度を利用すると、自己負担割合が原則1割になります。
さらに重要なのが、所得に応じた月額負担上限額が設定されることです。これは、1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定の金額を超えないようにする仕組みです。上限額は、ご自身の所得や世帯の状況によって細かく設定されています。
例えば、
低所得の方: 月額負担上限額が数千円程度に設定されている場合があります。
一定以上の所得がある方: 月額負担上限額が1万円程度に設定されている場合があります。
この上限額があることで、「今月はたくさん通院したから医療費が大変なことになるかも…」という不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境が整います。
通院で発生する医療費(診療や薬代)のほか、訪問診療・往診・デイケア・訪問看護なども対象になります。
当院の施設基準・加算について (九州厚生局熊本事務所への届け出事項等)
当院は、九州厚生局に届け出をしている保険医療機関です。
当院及び当院の医師は療養担当規則に沿って療養の給付を行います。当院では、「かかりつけ医」機能を有するクリニックとして、以下の取り組みを行っております。
- 受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合がございます。
- 必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させて頂きます。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
- 福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
療養生活継続支援加算(療活継)第18号
当院では、患者さまの安心・安全な療養生活を支えるため、以下の体制を整備しております。
-
在宅医療に関わる多職種(医師、看護師、薬剤師、ケアマネジャー等)との連携体制を整備し、必要に応じて情報共有を行っています。
-
地域包括ケアを担う医療機関として、退院後や在宅療養中の患者さまが安心して生活を継続できるよう支援しています。
-
必要に応じて、訪問看護や訪問薬剤管理指導などの在宅サービスとの連携を図り、療養生活に関する助言・調整を行っています。
-
緊急時には速やかな対応ができるよう、地域との連携体制を構築しています。
こころの連携指導料(Ⅱ)(こ連指Ⅱ)第26号
当院は、患者さまが安心して在宅療養を継続できるよう、医療・福祉機関との連携体制を整え、必要な支援を行っております。
-
患者さまに対して、主治医と連携しながら、適切な在宅医療・療養支援を実施しています。
-
精神科医療機関や訪問看護ステーション等との情報共有を行い、継続的なケアを支援しています。
-
こころの健康に関するご相談や生活上の困りごとにも、医師・看護師・相談員等が連携して対応いたします。
明細書発行体制等加算
当院は療担規則に則り、医療の透明性向上と患者様への情報提供を目的に、診療報酬の算定項目、使用した薬剤名、実施した検査名などが記載された診療明細書を、領収証とともに無料で発行・交付しています。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
- 一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 -
当院は患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬又はリフィル処方箋の交付に対応可能です。
医療DX推進体制整備加算(医療DX)第335号
当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療をおこなっています。当院は情報通信機器を用いた診療に対応しておりますが、情報通信機器を用いた初診診療では向精神薬を処方しておりません。
当院は、厚生労働省が推進する医療DXの取り組みに賛同し、以下の体制を整備しております。
-
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
-
オンライン資格確認を通じて取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を、診療に活用しています。
-
電子処方箋を発行する体制を整備しています(※運用開始時期は追ってご案内いたします)。
-
電子カルテ情報共有サービスを活用する体制を有しています(※運用開始時期は追ってご案内いたします)。
-
医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう、職員の研修等を通じて体制整備を進めています。
今後も安全・安心で質の高い医療を提供できるよう、医療DXの推進に取り組んでまいります
医療情報取得加算
当院はマイナンバーカードによるオンライン資格確認に対応しています
受診された患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
通院・在宅精神療法
- (イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行います。
- (ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行います。
- (ハ) 介護保険に係る相談を行います。
- (ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員からの相談に適切に対応します。
- (ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行います。
- (ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行います。
- (ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行います。
- (チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行います。
- (リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えます。
情報通信機器を用いた診療について(情報通信)第99号
当院では初診でのオンライン診療(向精神薬の処方を含む)は行っておりません。
症状が安定している方を対象に情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を実施しております。オンライン診療の実施にあたっては、医師が医学的な観点からオンライン診療の実施の可否を判断します。ご希望の方は診察時に医師にご相談ください。
オンライン診療を実施する場合は、クリニクスアプリのインストール、アプリへのクレジットカードと保険証の登録をお願いします。また、診療費とは別に通信費使用1.200円をご負担いただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
〇当院は往診や訪問診療に対応しております。
患者さまのお宅に定期的に訪問して診察することができます。
寝たきりなどで通院がしづらい方、病院から退院して自宅療養中の方など、患者さまの状況に応じて対応いたします。ご不明な点などはご相談ください。
〇訪問診療を実施している患者様に関しては、他の医療施設、介護サービス事業者と連携しています
訪問診療実施患者様の状況に応じて、下記医療・介護施設と、きめ細やかな連携体制をとっています。
患者様同意の上、連携する施設間においてICTツールを用い、患者さまの診療情報等を共有しています。
在宅療養支援診療所・在宅時医学総合管理料 (在医総管)第661号
在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。
「第9」の1の(3)に算定する在宅支援診療所の点数を算定します。
ニコチン依存症管理料(ニコ)第408号
当院はニコチン依存症管理料の届け出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行っています。クリニック内とその周辺は全面禁煙ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
CT撮影及びMRI撮影(C・M)第580号
在宅持続陽圧呼吸法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算(遠隔持陽圧)第114号
ハイリスク妊産婦連携指導料2(ハイ妊連2)第11号
精神科退院時共同指導料1及び2(精退共)第11号
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
当院はこれらの施設基準に適合しています。
その他の指定について
・生活保護法指定医療機関
・指定自立支援医療機関
・指定難病医療機関
・指定小児慢性特定疾病医療機関